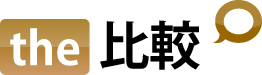※当サイトはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
子供と覚えておきたいインターネットの危険性とセキュリティ

突然ですが、子供がどのくらいインターネットを使っているかご存じでしょうか。
内閣府が実施した「平成30年度 青少年のインターネット利用環境」によるインターネットの利用状況を見ると、小学生で85.6%、中学生だと95.1%、高校生は99.0%と非常に高い割合でネットを利用しています。このように、子どももネットを利用することが、当たり前の時代となっています。
このような中、未就学児から大学生の子どもを持つ保護者を対象に実施されたアンケート調査では、子どものインターネット利用に関して、34%が「とても不安」、53%が「少し不安」と回答しており、合わせると87%、実に9割近くの保護者が子どものネット利用に不安を感じています。
使い方によっては危険な道具にもなってしまうインターネットですが、どんな危険があるかを知り、きちんと対策をするならば、怖がる必要はありません。
このページでは、子どもがインターネットを利用する上で、どのような危険が存在するかや、そのセキュリティ対策方法等について説明します。
目次
ネット利用の危険
- SNSに潜む危険
- 不正アクセス
- アダルト系のサイト
- 児童ポルノ・リベンジポルノ
- 掲示板
- 迷惑メール
- 出会い系(マッチング)サイトやアプリ
- 著作権法違反
- Wi-Fiスポットの利用
- ランサムウェア
- マルウェア(ウイルスやボット等)
- オンラインゲーム
- ネット中毒・ネット依存
- ネットショッピング
- その他の不適切な利用
対策方法
親子で話し合っておきたいこと
ネット利用時の危険
子どもがインターネットを利用するときに潜む危険は実に様々です。インターネットを使うと、簡単に情報を発信できるので、子どもが被害者になる危険だけでなく、加害者になってしまう、という危険もあります。
子どもをネットの危険から守るための大事な一歩は、インターネットを利用するときの危険を保護者が正しく理解しておくことです。ここでは、ネットの様々な利用シーンにおける危険を事例と共に紹介します。
SNSに潜む危険

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、インターネットを介して人と人とがつながるコミュニケーションツールです。例えば、LINE、Facebook、Twitter、Instagram、TikTokなど実に様々な形態があります。何かのコンテンツを楽しむというだけでなく、自分から情報を発信することも可能な点が、大きな特徴です。
SNSは、コミュニケーションをとるうえでとても便利で、面白い反面、いろいろな危険が潜んでおり、被害に遭う子どもの数は年々増加しています。子どもたちにとって不可欠なツールとなっているので、SNSを使わせないというのではなく、賢く、上手にSNSを使えるように教えてあげることが大切です。
個人情報流出
事例友人に誘われて動画を撮り、TikTokに投稿した。数日後、Twitterのダイレクトメールで、知らない人から連絡がきた。TikTok動画から、大学やサークル、出身高校、名前、Twitterアカウントなどの個人情報を特定されており、自宅などまで特定されるのではないかと不安を感じた。
コメント直接個人情報を書き込んでいなくても、投稿した写真や動画に映っている情報(制服、背景など)を元に、個人情報や自分の生活圏、最悪の場合は自宅の場所までも特定されてしまうことがあります。瞳に映っていたものから個人情報が特定されてしまった、という事例もあるほどです。
さらに、自分が投稿したものから、知人や友人の個人情報が漏れてしまう危険があることも認識しておきましょう。
ネットいじめ
事例中傷されたり、嫌なあだ名で呼ばれたりするなどのいじめをSNS上で受けていた生徒が自殺に追い込まれるという事件が発生。その他にも、SNS上でのいじめで不登校になったり、心に傷を負うという事例が後を絶たない。

コメントSNSを使用したネットいじめは、とても陰湿で、子どもにとって予想以上に大きなダメージとなることがあります。その手法は様々ですが、例えば、以下のようなものがあります。
グループチャットで自分が発言しても、みんなから一斉に無視される。グループ内の複数人から暴言を投稿される。グループチャットから一人だけ外される。自分を除くグループメンバーが別のチャットグループを作成しており、陰で悪口を言われる。仲がいいと思っていた友人が、SNS上で他の人に自分の悪口を言っていた。24時間で投稿が消えるストーリー機能を使って、嫌がらせをされる。写真を撮られ、加工してSNS上に勝手にアップされる。
このようなSNSを使ったネットいじめが増えており、これからも新しい方法が出てくることでしょう。
SNSのグループチャット内という閉じられた空間でのいじめのため、先生や親が気付きにくいのも特徴となっています。ちょっとした行き違いなどで簡単にいじめの対象になってしまうことや、冗談のつもりがいじめの加害者になっている、ということもあります。
参考サイト
新潟の高校生自殺、「SNS上でいじめ」 学校など会見 - 朝日新聞
高2女子は“ネットいじめ”が原因で自殺か? 陰湿化するネットいじめの特徴と対策は - FNN
「表は仲良し、裏アカでは悪口…」ネットいじめが過去最多に。 - buzzfeed
どうしたら子供を「LINEいじめ」から守れるか。 - TONE MOBILE
違法薬物の入手経路に
事例SNSを通じて大麻を入手、所持したとして22人が摘発され、その中には高校生も含まれていた。機密性が高く、メッセージを削除できる「テレグラム」というSNSを使用して薬物の売買が行われていた模様。
コメントSNSを通して、思ってもいなかった危険が身近になってしまうことがあります。隠語を用いたり、親の使い慣れていないSNSツールを使用されると、親が気付きにくいことも考えられます。
参考サイト
中越地方の高校生含む20人超、大麻で摘発 - 新潟日報
誘い出し
事例1大阪市の小学6年生の女児が行方不明になり、数日後に栃木県で保護されました。連れ去った男は、女児とTwitterで知り合いとなり、ダイレクトメッセージ機能を使用して、女児を誘い出し、監禁していました。
事例2座間市において、女子高生3人を含む9人の方が殺害される事件が発生。加害者は、自殺願望等SNSに投稿していた被害者と接触して会う約束をし、殺害に及んでいました。

コメント悩みを抱えていたり、家出を考えていることをSNSに投稿する子どもたちに、言葉巧みに近づき、子どもが信頼したところで、誘い出すという事件が増えています。SNS上では身分や正体を隠すのが容易です。そのため、同年代の同性の相手とやり取りをしていると思っていたり、すごく親切な人だと感じていても、実際には良くない目的を持った大人が子どもたちを狙って接触しているのかもしれません。
さらに、家出をした子どもたちが、無償で寝食を提供してくれる人(=神)をSNSを通して探す、「神待ち」という社会問題もあります。
SNSには知らない人ともつながりやすく、性的な被害や、身体的な被害、場合によっては命が危険にさらされることもあることを意識しましょう。
参考サイト
《未成年者誘拐続出》"神待ち"家出少女を待ち受ける男たちの本性 - 文春オンライン
援助交際・パパ活・ママ活
事例15歳の少女がTwitter上でパパ活の相手を募集。実際に65歳の男性がこの少女とみだらな行為をしたとして逮捕される。
コメント以前は、マッチングサイト等がよく使われていたようですが、18歳未満の登録が原則禁止となったため、未成年の子どもが援助交際やパパ活・ママ活の相手を募る主な手段として、TwitterなどのSNSが使われているようです。
援助交際やパパ活・ママ活で逮捕されるのは大人の場合が多いですが、子どもの側にも性的被害、暴力行為、録画・録音による脅迫など、大きなリスクが伴います。リスクを意識せずに、目先のお金目的や、面白半分で手を出すことがないように注意しましょう。
なりすまし
事例同級生からInstagramのアカウントを変更したか尋ねられた。身に覚えがなかったので、確認すると、自分になりすましているアカウントが存在しており、卑猥な投稿などがされていた。
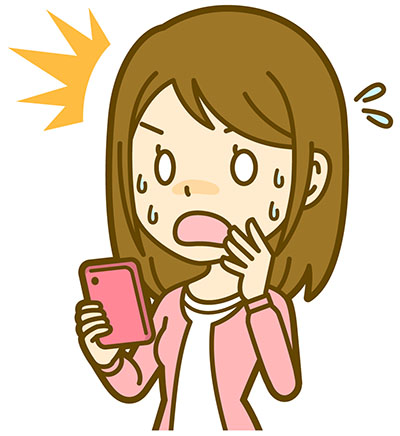
コメントなりすましたアカウントを使用して、他のユーザーへの脅迫や嫌がらせの投稿が行われたり、なりすまされたアカウントで不適切な投稿が行われると、評判や信用が損なわれたり、友人とのトラブルに発展する可能性もあります。
学校、名前、生年月日などを知られている身近な人からなりすまされる、ということも多いようです。なりすましに気付いたら、慌てず、適切に対処しましょう。
SNS空き巣
事例「高須クリニック」の高須克弥院長が、「明後日から台北の神社に台湾加油しに行きます。」とツイートしました。この留守のタイミングを狙われて、空き巣被害に遭い、金塊やパソコンなど3,000万円相当以上の被害を受けました。

コメント上記は子どもの例ではありませんが、子どもがSNSに上げた情報から、家が留守になるタイミングや、家族で旅行に出かけていることなどが明らかになると、空き巣被害に遭う危険が高まります。何気ない投稿や、写真などからも、自宅の場所、生活パターン(留守にしている時間帯)が漏れてしまう危険があります。ネット内だけでなく、実生活にも被害が及ぶことがありますので、十分注意しましょう。
参考サイト
「留守なう」 空き巣見てる SNS投稿、注意を - 東京新聞
その他
2019年8月から、LINEにはオープンチャットという新しい機能が追加されました。これは、友達ではないLINEユーザーともつながれるチャット機能です。開始直後から、わいせつな内容や、出会い系のようなタイトルのトークルームなど、子どもに使わせたくないような状態が多く見られました。LINE側も次々と対策を行ってはいますが、完全にコントロールできている訳でもないようです。
このように、新しいサービスが登場したりすることで、知らない人とも簡単につながることができるフィールドが増えることが予想されます。
保護者が、最近子どもたちの間で何が流行っているかなどを尋ねて、子どもの使用しているサービスに関心を持ち、実際に使ってみたりして、一緒に安全策を考えていくことが重要だと思います。
不正アクセス
事例ルールを守ってオンラインゲームを楽しんでいたが、ある時ゲームにログインしてみると、頑張って手に入れたアイテムがなくなっていた。誰かに不正にログインされて、アイテムが盗まれていた。
コメントSNS、オンラインゲームなど、IDとパスワードでログインして使用する全てのサービスにおいて、不正アクセスの危険があります。例えば、SNSアカウントに不正にログインされて乗っ取られてしまうと、上記にあるような、なりすまし被害にもつながります。場合によっては、個人情報が盗まれたり、金銭的な被害を被ることもあります。
または、親しい友人の使っているIDとパスワードを知ってしまい、軽い気持ちで友人のアカウントにログインしたり、学年が上がってくると、腕試しでハッキングしてみた、というような不正アクセスの加害者になってしまうということもあります。
参考サイト
不正アクセスとは?被害事例、被害有無のチェック方法と有効な対策 - Norton Blog
アダルト系のサイト
有害情報
事例小学6年生の子どもに連絡用のスマホを渡したところ、ネットの閲覧履歴にアダルトサイトと思われる言葉が並んでいた。確認すると、過激な性描写が続くアニメ系のサイトを見ていた。

コメント好奇心が非常に強く、学校の友達からも様々な情報を仕入れてくるため、親が予想していない年齢の子どもでも有害な情報に接する危険があります。男児、女児の区別なく、性に関する知識がない子どもを、現実とは異なるゆがんだ表現から守るためには、低年齢の時からの対応がおすすめです。
参考サイト
小6息子が過激な有害サイト、言葉失う親「怖さ知った」 - 朝日新聞
架空請求
事例アダルトサイトを見ていたら、「有料登録完了」と表示され、お金を請求された。さらに、焦って退会申請のメールを送ってしまった。その後、お客様窓口に連絡するように、連絡しない場合は自宅に手紙などの郵送物を送る、という内容のメールが届いた。

コメントアダルト系サイトのように、親に相談しにくい状況では、自分で解決しようと焦ってしまい、電話番号や名前、住所などの個人情報を送信してしまう危険もあります。高額のお金を持っていないとしても、不要な心配を増やさないためにも、事前に対策を取っておきましょう。
参考サイト
児童ポルノ・リベンジポルノ
事例1女子中学生が、ネットで知り合った人から、連絡先や写真をばらまかれたくなければ、裸画像を送るように脅され、実際に自分の裸の画像を送ってしまった。
事例2高校生の女子は、交際相手にお願いされて恥ずかしい写真を送っていた。しばらく後に、女子が別れ話を持ちかけると、交際相手の男子は女子の恥ずかしい写真を同級生に送り付け、次々と広がってしまった。
コメントひと時の恋心や、ノリで恥ずかしい写真などを送ってしまうと、意図していなかった方法で使用されてしまう危険があります。恥ずかしい写真や動画を送ってしまったあとでは、取り返しがつかないことが多いです。
これは女子だけの危険ではありません。実際に、男子生徒も同じような被害に遭っているケースがあります。
掲示板
事例19歳のイケメン大学生になりすましたおじさんが、掲示板に書き込まれたLINE IDから女子中学生と知り合い、女子中学生のLINEグループに招待してもらう。LINEグループ内の女子中学生たちに言葉巧みに話しかけ、裸の写真を送らせていた。約130人の女子中学生が裸の写真を送信させられていた。
コメント掲示板と言うと、一昔前に流行ったサービスのように感じるかもしれません。実際に、学校裏サイトなどの掲示板を使ったいじめなどは、多くがSNSに取って代わられているようです。
それでも、掲示板に関係した危険がなくなったわけではありません。「LINE掲示板」などの、SNSのID交換を目的とした掲示板は今でも運用されています。これは、LINEなどの公式サービスとは一切関係がなく、年齢確認などなくだれでも利用できるため、性犯罪や詐欺など思わぬ危険に巻き込まれる可能性が非常に高いです。
迷惑メール
事例「【警報】 あなたのAppleIDはリセットされ、一時的にロックされています」というメールが届いたので、急いでメールのリンクからApple IDとパスワードを入力した。しかし、このメールは偽メールだったため、Apple IDとパスワードを盗まれてしまった。

コメント迷惑メールは、今や古典的となった手法ですが、受け取るタイミングなどによっては、本物と思ってしまうことがあります。また、最近では、スマホのSMSが悪用されることもあります。
個人情報や、ログイン情報を盗む、フィッシング詐欺の手段として、今でもメールが使われることがあるので、引き続き油断なく警戒する必要があるでしょう。
参考サイト
宅配業者装うSMSに注意 スマホ乗っ取られ詐欺に悪用 - 朝日新聞
出会い系(マッチング)サイトやアプリ
事例ある中高生を対象にしたアンケートで、スマホを持った生徒の半数以上が、出会い系サイトやアプリの広告や情報を目にすることが増えたと述べています。また、23%が出会い系サイトやアプリがどのようなサービスなのか興味を持っており、さらに15%ほどが実際に出会い系サイトやアプリを閲覧したことがある、と回答しています。
コメントネットでの新たな出会いを求める主なプラットフォームはSNSへと移行していますが、それでも上述のアンケート結果が示すように、出会い系サイトやアプリに興味を持つ子どもたちも少なくないようです。
多くのマッチングアプリでは身分証明書などでの年齢確認が行われますが、中には年齢確認がされないマッチングアプリも存在します。
マッチングサイトやアプリの使用には、性犯罪などの被害者になるリスクが伴いますし、そもそも18歳未満の出会い系サイトやアプリの使用は法律で禁止されています。
著作権法違反
事例中学生がマンガをYouTubeに無断でアップロードし、逮捕される。
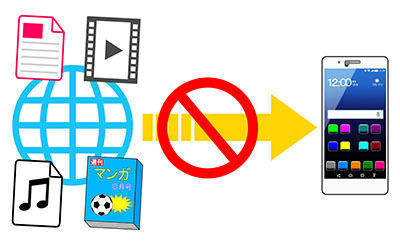
コメントネットを使うと、ダウンロード、アップロード、拡散などが簡単にできてしまいます。悪気がなくても、作者の権利を侵害してしまうことは違法となります。
上記の事例のように、逮捕されることは稀かもしれませんが、ネット上の写真・イラスト・音楽、CDから取り込んだ音楽、漫画などを他の人に送信する、といったことは違法アップロードとなります。
また、ネット上にある海賊版の音楽や映画をダウンロードすることも違法です。現在では、「漫画村」で有名になった漫画の海賊版サイトからのダウンロードも違法となる可能性が高いです。
Wi-Fiスポットの利用
事例パケット代を節約するため、カフェやコンビニなどのフリーWi-Fiをできるだけ使っていた。ある時、使っていたSNSのログイン情報が悪意のあるWi-Fiスポット経由で盗聴されてしまい、アカウントを乗っ取られてしまった。

コメント悪意のあるWi-Fiスポットに接続してしまうと、簡単に大切な情報が覗かれてしまいます。子どもなので、ネットショッピングや、クレジットカードの利用などはほとんどないため金銭的な被害はないとしても、SNSなどのログイン情報や、個人情報を盗まれることも危険です。SNSのアカウントが詐欺行為に使用されたり、つながっている友人にも迷惑が及ぶことがあり、自分だけの被害では済まない場合もあります。
ランサムウェア
事例面白そうなゲームアプリが今だけ無料だったので、インストールした。アプリを起動すると、端末がロックされ、お金を払わないとデータが消去される、というメッセージが表示された。
コメントランサムウェアと言うと、2017年に流行ったWannaCryがとても有名です。ランサムウェアの被害に遭うと、写真や連絡先などの大切なデータが失われる可能性が高いです。お金を払っても、勝手に暗号化されたデータを安全に取り戻せるという保証はありません。パソコンだけでなく、スマホやタブレット端末も、ランサムウェアの被害に遭う可能性があります。
怪しいアプリなどをインストールしないように気を付けましょう。
マルウェア(ウイルスやボット等)
事例マルウェアには様々な種類がありますが、例えば、有用なアプリを装っていながら、実際には個人情報を無断で送信したり、デバイスを乗っ取るためのバックドアを仕掛けたりする、トロイの木馬などがあります。

コメントウイルスやボットを含むマルウェアによる被害は、子どもだけではなく、ネットを使う誰もが注意する必要がある危険です。パソコンだけでなく、スマホやタブレット端末にも感染するリスクがあります。
ウイルスに感染すると、個人情報が盗まれてしまったり、大切なデータが消えてしまったりする危険があります。また、ボットウイルスに感染すると、デバイスを知らないうちに操られてしまい、サイバー攻撃に加担させられたり、迷惑メールの送信元にされる、といった被害を受けることがあります。
オンラインゲーム
オンラインゲームは、ネットを通して世界中の人とつながり、見知らぬ人と対戦したり、複数のプレイヤーが一緒に冒険することなどができ、幅広い人気を得ています。
しかし、そこには以前のテレビゲームとは違った、オンラインゲームならではの危険も潜んでいます。
チャット機能
事例福岡県の中学生が、オンラインゲーム「荒野行動」で知り合った人から大麻の購入を誘われる。
コメントオンラインゲームの多くが、プレイヤー同士でコミュニケーションをとるための音声や文字のチャット機能を備えています。また、スマホのGPS機能を利用して、自分の近くにいるプレイヤーを探すことができるゲームもあります。
SNSで突然知らない人から声をかけられたら怪しむ場合でも、同じゲームをプレイしている人から声をかけられると、友達と認識してしまい、やり取りをしているうちに、怪しい誘いを受けるということも考えられます。また、ゲームのチャット機能は、LINEやFacebookといったSNSよりも、親の目が届きにくいという点も落とし穴となるかもしれません。
参考サイト
大麻購入、スマホゲームで中学生誘う 福岡の学校が注意呼び掛け - 西日本新聞
スマホゲーム「荒野行動」を通じ中学生に大麻購入を勧誘 “スマホから忍び寄る危険”を防ぐには? - FNN PRIME
高額請求
事例小学生の子どもが母親のスマホを借りて、ゲームをプレイ。アイテムが欲しいときは母親に相談して、パスワードを入力してもらって数回購入していたが、翌月10万円を超える請求が来る。
コメント上の事例では、パスワード入力後の数分間は、パスワードの再入力が必要なく、自由に購入できるような設定になっていたことが問題でした。パスワードの有効時間の設定を見直すことで、同じような危険を回避できます。
また、課金式のオンラインゲームは、お金を使えば使うほど有利にゲームを進めることができるように作られています。1回の課金金額が比較的安かったり、実際にお金を手渡しで支払うわけではないため、購入しているという感覚が薄くなる、という理由から、思った以上に課金しすぎてしまうこともあるようです。
ネット中毒・ネット依存
事例中学生からオンラインゲームに熱中し、生活のすべてがネットゲーム優先に。別人のようになってしまい、学校にも行かなくなり、注意されると暴言や暴力を振るうようになる。

コメントネット依存・ネット中毒になると、通常の生活にも大きな影響が及び、インターネットやネットゲームから離れることができなくなります。その後の人生を大きく狂わせてしまうこともあるので、重症化する前に手を打つ必要があります。
ネットショッピング
事例子供が勝手に親のクレジットカードを使って、ネットショッピングで高額の買い物をしてしまった。
コメントこのような場合、法律的には契約の取り消し請求が可能な場合があります。ただし、クレジットカードの所有者には、善管注意義務があります。つまり、カードをしっかりと管理する義務があり、これをちゃんと果たしていなくて不正に使用された場合、カード会社からの保証は受けることができません。
オンラインゲームの課金についても同様です。
参考サイト
課金トラブルを防止するには?子供のカード無断利用に注意! - Orico
その他の危険
事例子どもがゲーム機や音楽プレイヤーでこっそりSNSを利用している場合がある。
コメント最近のゲーム機や、音楽プレイヤーは高機能になり、スマホとほぼ同じ機能を備えているものもあります。例えば、人気あるNintendo SwitchではSNS投稿ができたり、iPod touchだとほとんどiPhoneと同じようにネットやアプリが使えたりします。
保護者が、ウェブ閲覧やSNSの利用を想定していない場合、知らないうちに子どもがネット上の危険の被害者になっていることがあるようです。子どもの持っているゲーム機や音楽プレイヤーでも、ネットやSNSが利用可能か確認し、必要な設定をすることで子どもを守りましょう。
参考サイト
対策方法
ここまで取り上げたような、様々なネット上の危険から子どもたちを守るために、具体的な対策を取る必要があります。
まずは、デバイスを準備するときにしてあげたい設定や、保護するために活用できるアプリなどについてご紹介します。
OSを更新して、いつも最新の状態に
Windows 、macOS、Android、iOS、iPadOSなどのOS、メールやインターネットに使用するアプリなどのプログラムには、脆弱性という弱点が発見される場合が珍しくありません。
ソフトウェアの開発者は、脆弱性が発見されると、修正プログラムを配布することで、弱点を悪用されないように対応します。そのため、OSやアプリを定期的にアップデートし、最新の状態に保つことが重要です。
多くのシステムで、これらの更新を自動的に適用する設定を選択できるので、必要に応じてこのような設定も活用することもできます。
また、これらの更新は無期限で行われるわけではありません。例えば、Windows 7のサポートは2020年1月14日に終了し、以後はセキュリティ更新はなされません。セキュリティの面を考慮すると、サポートが終了したOSやアプリの使用は控えた方がいいでしょう。
参考サイト
Windows 10 を更新する - マイクロソフト
Macを最新の状態に保つ - Apple
Androidのバージョンを確認して更新する - Google
iPhone、iPad、iPod touch をアップデートする - Apple
子ども用のアカウントを作成
WindowsやMacといったパソコンを子どもと共有するときでも、iPhoneやAndroid端末を子どもに持たせるときでも、子ども用のアカウントを作成するようにしましょう。
パソコンを共有する場合は、大人用と子ども用のアカウントを分けておくことで、大切なデータの誤削除や、ウイルスに感染してしまった場合のリスクなどを低減することができます。
また、子ども用のアカウントできちんと設定しておくことで、アクセスできるコンテンツの制限、使用時間の制限、使用するアプリの制限、アプリのインストールの禁止などの機能制限を加えたり、実際の使用状況を確認できたりします。
セキュリティ対策ソフトを活用
ウイルス、マルウェア、フィッシング詐欺、怪しいアプリなどからの被害を防ぐうえで、セキュリティ対策ソフトは有効です。
最近は、PC、Mac、Android、iOSのマルチOSに対応した複数台に導入できるパッケージが増えています。家族内であれば無制限にインストールできるものなどもありますので、家族の持つデバイスのすべてに導入して、みんなでセキュリティを高めておくことをおすすめします。
ただし、セキュリティソフトを入れているからと言って、100%安全という訳でもありません。子どもたちがネットを使う上での注意点も継続的に教えていく必要があります。
なお、セキュリティソフトは、メーカーによって性能や、特化した部分が異なります。下のセキュリティソフトの比較をソフトを選ぶ時の参考にしてください。

パソコンに必須のセキュリティソフトの比較ページ。セキュリティソフトの選び方や、比較一覧表、用途ごとのおすすめ製品などを掲載。
ペアレンタルコントロール機能を設定
ペアレンタルコントロールとは、フィルタリングや、デバイスの使用時間制限などを加えることで、保護者が子どものネットやデバイスの使用をコントロールするためのソフトです。
2018年2月から、スマホの使用者が18歳未満である場合、フィルタリングの設定を行うことが義務化されていますが、使用率はあまり高くないのが実情のようです。
格安SIMなどを保護者が契約して子どもに使用させる場合などは、保護者側での対応が必要な場合が多いです。また、このフィルタリングの義務化はスマホに限定されているので、PC、Mac、タブレット端末なども利用する場合も、必要であれば保護者が導入し、設定しなければいけません。
Windows、macOS、Android、iOSであれば、下の参考サイトに挙げているように、各社が何らかのペアレンタルコントロール機能を提供しています。これらは無料で使用することができます。
ただし、それぞれの機能や操作がOSによって異なるため、Windows PCと、Androidのスマホというように、複数のデバイスを使用している場合などは、設定も面倒です。思ったような制限がかけられないということもあるでしょう。
おすすめは、ペアレンタルコントロール機能を備えた、セキュリティ対策ソフトの導入です。特に、ノートンセキュリティ プレミアムは、不適切なサイトのブロック精度も高く、きめ細かな機能が搭載されており、親子ともども使いやすいです。
the比較でも、「セキュリティソフトのペアレンタルコントロールの比較」という記事がありますので、こちらも参考になさってください。
初期の設定などが面倒かもしれませんが、子どもを守るために、ペアレンタルコントロール機能を是非活用しましょう。
参考サイト
フィルタリングをご存知ですか - 総務省
Microsoftファミリ グループとは - マイクロソフト
Macで子供のスクリーンタイムを設定する - Apple
お子様のiPhone、iPad、iPod touchでペアレンタルコントロールを使う - Apple
ファミリーリンク - Google
ネットの利用状況を定期的に確認

セキュリティ対策ソフトの導入や、ペアレンタルコントロール機能の設定が終わっても、これで終了ではありません。
実際にパソコンやスマホを使うようになっても、どんなサイトを見ているか、どんなアプリを使用しているか、SNSでどんな人とつながっているか、どのくらいの時間ネットを利用しているか、といったことを時々確認して、ネット利用に潜むリスクを思い出させてあげることが大切です。
この点で、レポート機能を備えたペアレンタルコントロールソフトは役立ちます。子どもが見たサイトのURL、ダウンロードしたアプリ、使用時間、ブロックされたサイトのURLなどを保護者のデバイスで確認できるものもあります。子どもを監視するわけではありませんが、子どもを危険から守るために、このような機能も活用しつつ、子どもがネットを楽しく活用できるようにサポートしてあげましょう。
親子で話し合っておきたいこと

セキュリティアプリや、ペアレンタルコントロール機能などの対策だけでは、子どもをネット上の危険から守る点で不十分です。実際には、ネット上の危険や、身を守るための方法などについて子どもと話して、教えることが最大の防御となります。
参考サイトでは、ネット上の危険のいくつかがイメージしやすく紹介されています。親子で話し合うための道具にしてみてください。
具体的に、どんなことを子どもと話し合っておくことができるか、以下にご紹介します。
ネット利用のマナー
通常の社会での生活にもいろいろなマナーがあるように、ネットの中でもマナーがあり、ネチケットと呼ばれることもあります。トラブルを避けるためにも、このネット上のマナーと、マナーを守る大切さを子どもにも教えましょう。
例えば、ネチケットには次のようなことが含まれます。
・本人に直接言えないことは書かない(相手の気持ちを考え、思いやる)
・テレビや新聞に載せられると恥ずかしい写真や動画は投稿しない
・友達のプライバシーを尊重する
・友達の失敗を大げさに指摘したり、広めたりしない
・メールやメッセージを送る前に、内容や送信先を確認する
他にもたくさんあると思いますが、基本的には、実生活でしないことはネットでもしない、相手の気持ちを思いやるということに集約できるかもしれません。
下の参考サイトには、ネチケットを教えるための教材となるページもあります。子どもが幼い時から教えてあげるといいと思います。
ネットの匿名性
ネットの匿名性については、2つの側面があります。相手側と自分の側です。ネットの危険を避けるためには、それぞれ、匿名性については次のように考えておくといいと思います。
相手側の匿名性
相手側の個人情報は隠しやすく、公開されている情報が本当の情報かは分かりにくいです。
例えば、ネットサイトの管理人や、SNS上で声をかけてくる見知らぬ人の場合、名前、性別、年齢などは容易に偽ることができます。そのため、SNSでつながった会ったことのない人が、同年代の同性で、優しくて親切な人だと思っていても、実際にはかなり年上の変質者的な大人で、よくない意図を持っているということが少なくありません。そして、このことはSNS上のやり取りでは見抜くことが困難です。
ネット上では、相手の身分や正体を簡単に隠せるということと、そのリスクを子どもにもしっかり理解して欲しいものです。
自分の側の匿名性
自分の側の匿名性は、意外と高くありません。
例えば、SNSなどで裏アカウントを作って、人の悪口などを言っていると、案外すぐに本人が特定されてしまったりします。また、ばれないと思って、ネット上で法を犯すような行動をとってしまうと、警察機関などは簡単に人物を特定することができます。
一つの投稿だけでは個人を特定できなかったとしても、いくつかの投稿などの情報を組み合わせることで、個人を特定できてしまったりします。
自分のことを隠さないといけないようなことは、ネット上でもしないように教えてあげましょう。
個人情報の扱い

個人情報には、名前、ニックネーム、学校・塾・スポーツチームなどの名称、顔写真、家の住所、誕生日、SNSのID、電話番号などたくさんのことが含まれています。これらの情報を、SNSやネット上で公開しないように教えましょう。もちろん、むやみに人に教えてもダメです。
注意する点として、個人情報を書き込んではいないものの、SNSなどにアップした写真や動画に映りこんでいるものや、建物などの背景から、自宅の場所や学校など、個人情報が洩れることがあります。
また、自分の情報だけでなく、家族や友達の個人情報も、同じように大切にしないといけないことも伝えましょう。
IDやパスワードの管理

SNSやオンラインゲームなどネット上のサービスにログインするために、IDやパスワードは不可欠ですが、子どもはその重要性にあまり気付いていない場合があります。IDとパスワードの扱いに関して、次のようなことを教えましょう。
・友達にパスワードを教えない:どんなに仲が良くても、パスワードは教えません
・パスワードの使い回しは避ける:一つのアカウント情報が漏れてしまうと、他のサービスのアカウントまで被害に遭うかもしれません
・友達の端末を借りてログインすることは極力避ける:友達の端末にログイン情報が保存されてしまったり、ログアウトを忘れて、間違って自分のアカウントを使われるかもしれません
・アカウントへのログインを促すような偽メールやSMSに注意する:そのようなメールのほとんどがフィッシング詐欺メールです
子どもの年齢に応じて、自分でパスワードを管理することも教えていきたいですが、幼いうちは、親がパスワードを管理して、必要な時に入力してあげるのも一つの方法です。
SNS利用の注意点
まず、SNSのプライバシー設定やセキュリティ設定を確認して、投稿の公開範囲、自分を検索できる人などを制限しましょう。ウイルスバスター モバイルなどのソフトを使用して、設定のチェックを行うこともできますが、FacebookとTwitterに限られています。子どもが使用するサービスに合わせて、保護者の方が設定を見直す必要があります。
加えて、SNSを利用するうえで注意事項を子どもに教えてあげましょう。
・実際に会ったことのない人、知らない人を友達登録しない
・人を傷つけることや、直接言えないようなことを書き込まない
・自分や家族、友達の個人情報を投稿しない
・家を留守にするような情報をリアルタイムで投稿しない
・文字でのやり取りなので、勘違いしたり、されたりしないように注意する
・怪しいダイレクトメッセージを開かない
代表的なことを挙げてみましたが、他にもたくさんの注意点があると思います。
主要なSNSでは、参考サイトにあるような、保護者のためのガイドが公開されています。このような資料を参考に、子どもと話し合ってみてください。
犯罪となる可能性がある行動

軽い気持ちでも、犯罪となるネット上の行動があることを教えましょう。
・児童ポルノ製造・提供罪:交際相手などの裸の写真などを撮ったり、送らせたりし、SNSで拡散する。または、友達から送られてきた子どもの卑猥な写真を拡散するだけでも、児童ポルノ提供罪が適用される場合があります。
・不正アクセス行為の禁止:他人のログイン情報を使って不正にログインすることは、不正アクセス禁止法違反になります。
・傷害罪・名誉棄損罪:うそや悪口をSNSやネットに投稿し、相手を傷つける行為は、名誉棄損罪、侮辱罪、傷害罪に問われる可能性があります。
・著作権法違反:著作物(音楽、動画、写真、歌詞など)を無断でアップロードしたり、海賊版をダウンロードすることは、著作権の侵害となります。
このような情報は、子どもを加害者にしないだけでなく、子どもをネット上のいじめや危険から守るためにも使うことができます。
デジタルタトゥー
デジタルタトゥーとは、一度ネットに投稿した個人情報や写真などは、タトゥーのようにしっかりと残ってしまい、完全に消し去ることがとても難しいということです。
取り返しのつかないことにならないように、何があっても、だれであっても、裸や恥ずかしい写真を送ることがないようにしましょう。メッセージや写真を投稿する前に、この情報が新聞やテレビに載っても困らないか、恥ずかしくないか考えるように教えてあげることができます。
Wi-Fiスポットの利用
通信量の節約のためとはいえ、パスワードのかかっていないフリーWi-Fiは使わないことが重要です。
また、悪意のあるWi-Fiスポットに勝手に接続してしまう危険もあるので、Wi-Fiへの自動接続設定をOFFにしておく方が安心です。
暗号化されているフリーWi-Fiでも危険がないわけではありません。VPNを使用する方法などがありますが、正しく判断することが難しいようであれば、Wi-Fiスポットは使用しない、というルールで子供を守ることが必要かもしれません。
困った時の対応
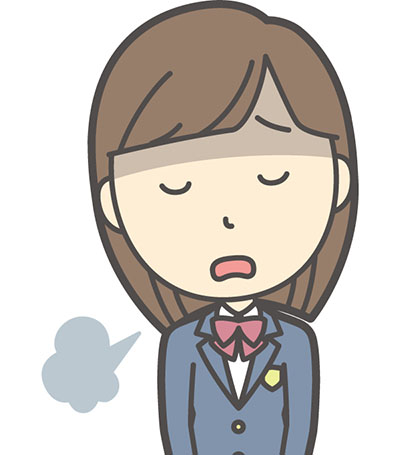
セキュリティアプリを導入したり、十分に注意して使っていたつもりでも、ネット利用における危険やトラブルに直面することがあるでしょう。子どもが自分だけでなんとかしようとすると、どんどん状況が悪化していく可能性が高いです。
失敗したと思ったり、恥ずかしく感じたりしたときでも、ネット上での困ったことを親に相談できるように、子どもとのホットラインを作っておきましょう。自分からは言い出しにくいので、時々親御さんから子どもに声をかけて、困ったことがないか確認してあげるのもいいと思います。
または、学校の先生や、公共の相談窓口など、信頼できる大人に相談することを教えておくことができるでしょう。
家庭のルール
ここまで紹介した、子どもと一緒に話し合っておきたいことを伝えたら、ネットを使うときの家族のルールとしてはっきりと決めごとをしておきましょう。
内閣府の調査では、保護者側はルールを決めていると思っていても、子どもはルールが決められていると思っていない、というギャップがあることが明らかになっています。
保護者が一方的にルールを決めてしまうよりも、やってはダメなこと、使用時間、課金や通信料の上限、困ったときは必ず大人に相談すること、ルールを守らなかった時どうするか、などを子どもと話し合って、お互いに納得してルールを決めると、より効果があるようです。明確にルールを決めて、継続的に話し合っていきましょう。
これらの情報を活用して、子どもたちが安全にネットライフを楽しむ手助けをしていただければと思います。
関連サイト
関連サイト
サイバー犯罪対策プロジェクト - 警察庁
子供の性被害対策 - 警察庁
子供たちが狙われています! - 警察庁
青少年有害環境対策 - 内閣府
ネットトラブル事例集 - 栃木県総合教育センター
実践!みんなのネットモラル塾 - 愛知県
関連リンク

不適切なサイトやアプリのブロック機能、位置情報確認、歩きスマホブロックなどの機能を備えたスマートフォン用アプリ。

国内の有名なセキュリティソフトについて、有害サイトをどれだけブロックできるかや、機能は豊富か、操作性は良いかなどを調査。

マルチデバイス版のセキュリティソフトの比較ページ。セキュリティソフトの選び方や、比較一覧表、用途ごとのおすすめ製品などを掲載。